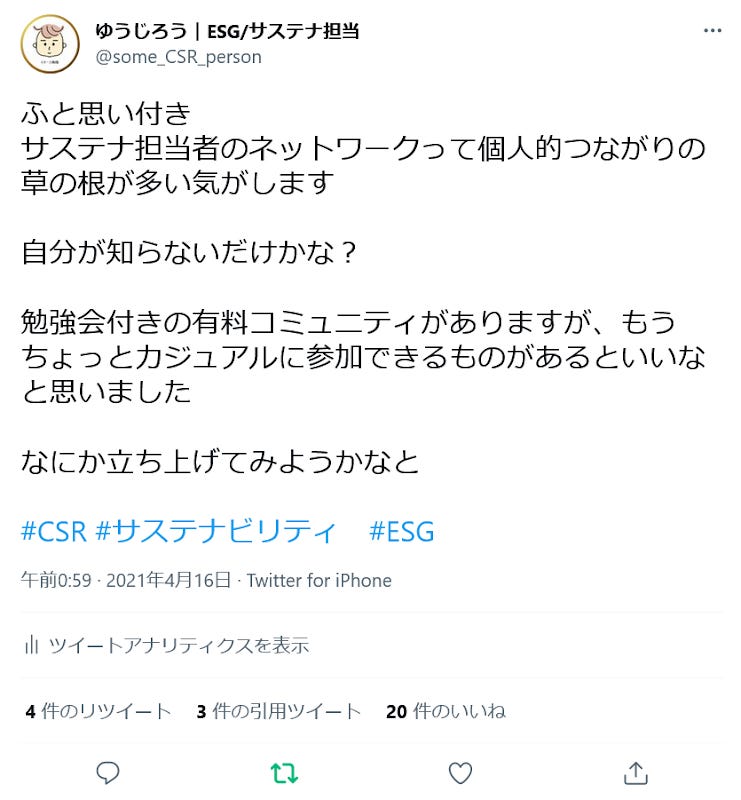事業会社のサステナ担当とサステナコンサルの違いとは?【インタビュー第2弾】
サステナブルコミュニティも運営するゆうじろうさんにインタビュー
近年、数多くの企業が「サステナビリティ部署」を設け始めました。しかし、実際に「サステナビリティ担当」として働くには、どのようなスキルが必要なのでしょうか?どのような仕事内容なのでしょうか?
そこで、bilityでは実際に企業のサステナビリティ担当の方にお話を伺い、「気候変動領域で働くこと」を考えるインタビュー企画をスタートしました!
→前回の記事はこちらから👋
IT企業で働くサステナビリティ担当者にインタビュー【第1弾】
第2弾は、事業会社のサステナビリティ部門で働く傍ら、サステナブルコミュニティを運営するゆうじろうさん( @some_CSR_person)にインタビュー!新卒でのサステナビリティコンサルについてのお話や、転職の経緯、コミュニティ発足のきっかけなど…「気候変動領域で働くこと」について、色々とお話を伺いました。
ーーまず最初に、事業会社のサステナビリティ部門で働いているとのことですが、具体的な仕事内容について教えてください。
サステナビリティに関わる全般を担当し、仕事は社内向け・社外向けに分かれています。
社内向けは、サステナビリティ活動目標の立案と推進に始まり、カーボンニュートラルやビジネスと人権、人的資本など個別テーマについて関係部門との折衝や実行支援を行っています。
社外向けには、統合報告書の制作やESG情報開示を担当しており、機関投資家とのESGミーティングやESG評価機関のスコア対応なども担っています。
ーー日々の呟きを拝見したところ、社内コミュニケーションに苦労している印象を受けました。仕事で難しい部分や、意識していることはありますか?
サステナビリティに関わる活動の多くはソフトローと呼ばれ、法律で制定されていないことが多く、罰則・規則がないことで強制力に欠けるのが難しいところです。気候変動ひとつとっても、実際に企業がやらなきゃいけないことは企業側の意思に委ねられます。
例えば、オーナー会社(創業者または創業家が経営している会社)であれば代表者の強い意志でサステナビリティを推進する企業もありますが、自分が勤めている会社では担当者が経営陣に向けて起案・提案をしています。
そのため、提案する際には、サステナビリティの専門知識ももっていない方に対して、どのように説明すればご理解・ご納得いただけるのかを意識しています。
ーーこれまで現職について伺ってきましたが、次は前職についてお話を聞かせてください。ツイートによると、サステナビリティを専門に扱うコンサルティング会社とのことでしたが、サステナコンサルでの仕事内容や、当時就職に至ったきっかけを教えてください。
前職では、ESG情報開示を支援する会社で働いていました。顧客の発行する統合報告書やサステナビリティレポート、ESGウェブサイトの企画提案から開示に至るプロジェクトマネジメントを担当しており、顧客企業のESG情報開示を充実させ投資家との建設的な対話の一助になることを意識していました。
大学時代、CSRに関するゼミで勉強しながらインターンもしていたこともあり、「自分の持っているスキルを最大限活かせる会社はどこか?」考えた上で、企業のサステナビリティを支援する会社を選んできました。
ーーなぜ転職しようと思いましたか?
支援側で顧客を支援することよりも、自らが組織の一員となり中から活動を推進したいという気持ちが強くなってきたことが一番の要因です。
最初のきっかけは、支援側から顧客へ提案をしていたことがなかなか通らないことがあり「なぜ通らないのか?」と思ったことです。
今にして思えば自分の提案レベルが低かったり、提案を受けた人がその後社内を説得していくところまでイメージできていなかったり反省することばかりですが、当時の私は「自分が顧客側にいたらどこまでできるのだろうか?」と思うようになりました。
そしてその気持ちが日を追うごとに強くなり、転職活動をした結果、現職にご縁をいただけました。
実際、転職して気付いたことが沢山あります。サステナビリティに関する社内浸透の難しさや社内関係者の巻き込み方や協力者の見つけ方など、組織の一員としてコトを動かすことの大変さを日々感じています。
ーー支援側(サステナビリティコンサル)と、実行側(事業会社のサステナビリティ担当)の具体的な違いについて詳しく教えてください。
支援側では「複数社を横断的にみる」ことができ、実行側では「自社を深くみる」ことができるのが大きな違いです。どちらが良い悪いという話ではなく、立場によって視点が変わるものであり、私は両方の立場を経験しているので、双方の気持ちがわかるのは強みだと感じています。
支援側だと複数顧客をもつので、自分では特定の顧客にもっと深く入り込みたいと思っても、他案件も同時に対応しなくてはいけない状況なので実行するのはとても難しかったです。
支援側と実行側を比較すると、自分は実行側の方がフィットしていたと感じています。あとは支援側は仕事の特性上、わりと長時間労働な環境だったので、それを変えたかったのもあります(笑)
ーー労働時間が長いとのことでしたがサステナコンサルでは具体的にはどのようにどのような流れで業務をしていたのでしょうか?
日中は顧客との打ち合わせやプロジェクトの調整業務などが続きます。
人によって対応方法は変わるかと思いますが、例えば、提案に対する顧客からのフィードバックが、クライアントの定時(=17時)に来た場合、17時以降にそのフィードバックに対応しなければいけない場面が度々ありました。
こうした対応が続く状況だと、構造的に長時間労働になりがちな環境だったなと感じています。あくまで私がその環境に適応できなかっただけの話なので、誤解がないように注意してほしいです。
ーー支援側と実行側の違いについてよく理解できました。現職で成し遂げたいことや今後のキャリアについて教えてください。
現在はサステナビリティ担当者として自社のサステナビリティレベルをいかに高められるかを考えています。
今後のキャリアについてはまだ模索していますが、サステナビリティ担当者のひとつのキャリアゴールとして、チーフサステナビリティオフィサー(CSO)になることが将来的な目標です。
チーフサステナビリティオフィサーになるために必要なスキルを得るために様々な経験や自己研鑽をしていきたいと考えています。なれるかどうかはまったくわかりませんけどね(笑)
ーーチーフサステナビリティオフィサー(CSO)は初めて聞きました!具体的にどんな役職でしょうか?
CSOは、会社の経営陣の中でサステナビリティの指針を中心となって決める役職です。日本企業でも数社、ポジションを設けている企業があります。会社のマネジメント体制によってポストの有無は変わりますが、今後も増えていくのではないでしょうか。
今後は意思決定側にまわって、思いを持ってサステナビリティへに取り組む人たちを応援していきたいです。
それでは次にゆうじろうさんの運営するサステナブルコミュニティについてお話を伺います。
※サステナブルコミュニティの概要についてはこちらのnotionがとてもわかりやすいです!興味のある方は是非ご一読いただき申込みフォームをご記入ください👀
〈概要〉
サステナビリティに関する関係者の交流を目的とした、slack上でのコミュニティ。個人を主とした相互学習型のコミュニティで、情報交換、勉強会や交流会などを行っている。
ーーそれでは、次にコミュニティについてお話を伺います。そもそもなぜこのようなコミュニティを設立したのでしょうか?きっかけを教えてください。
サステナブルコミュニティは、偶然と幸運がいくつも重なってできた非常に貴重な場だと捉えています。元々は社外の知り合いを数人つくりたかったのですが、結果として今のようなコミュニティに育っていきました。
発足したきっかけですが、コロナ前は集合形式のセミナーなどが数多くあり、隣の席に座った方と名刺交換をしてその後情報交換をするといった草の根のつながりがありました。しかし、コロナによってそういった機会が全く無くなったことに危機感を覚え、つながりをつくるきっかけとしてTwitterの活用を思い付きました。
当時はサステナビリティに関するニュースを発信するだけでしたが、フォロワーのなかに私と同じようなサステナビリティ担当者の方がおり、勇気を出してDMを送り、オンラインで情報交換の機会をつくることができました。
この体験をきっかけに、オンラインベースのコミュニケーションスペースが無いかと思いネットで探してみましたが、私の希望する運営を行っている先がなく、冗談半分でコミュニティ立ち上げの募集をTwitterでつぶやいたところ、募集1か月で約50人集まってしまいました(21年5月にコミュニティ立ち上げ)。
コミュニティ募集開始のツイート(21年4月16日)
このツイートにいいねをくれた方にDMを送り、一人ひとりとオンラインでご挨拶しました。
ーー1ヶ月で50人とはすごい人数ですね!隠れたニーズがあったのでしょうか?
私としても、予想外に集まってしまったな…という感覚が本音です…
強いて言うならば、人が集まった理由は3つあるかなと分析しています。
①コロナで横のつながりを欲するの潜在ニーズがあったこと
②ビジネスとせず現役のサス担がボランタリー運営していたこと
③Twitterアカウントでの情報発信を通じて真面目な印象を持っていただけたこと
3つ目についてですが、自分はTwitterでシンクタンクや省庁といった、割と硬めのニュースを日々流していたので、信頼感があったのかもしれません。
当初は5〜6名ぐらいを想定していたので想定外でしたが、これはちゃんと運営しなければダメだなと思い、コミュニティ運営に着手することになりました。
私自身、こういったコミュニティ運営経験がなかったので、メンバーほぼ全員とオンラインでご挨拶し、申し込んだきっかけややりたいことなどを伺って、それを実現するための運営をすることを意識しています。
ありがたいことに、コミュニティ立ち上げ後も新規の加入希望や既存メンバーからのご紹介などネットワークが広がっており、10月21日時点でslack登録人数は277名となっています。
ーーコミュニティの運営で意識していることを教えてください。
コミュニティには本当にたくさんの方々が参加してくださっています。事業会社のサステナビリティ担当が50~60人ほどで一番多いですね。
新規加入メンバーとのご挨拶をさせていただく際に、「所属の看板を降ろして、いち個人として参加していただきたい」とお伝えしており、大事にしているところです。
運営する中で、それぞれのポジションでみなさんが悩みを抱えていることがわかりました。孤軍奮闘していて、誰に悩みを言えばいいのかわからず辞めてしまった方もいます。気軽に相談する先があると、心理的な支えにもなる、そのためのコミュニティになればと思っています。
ーーサステナブルコミュニティでの目標や今後やりたいことなどありましたら教えてください!
サステナブルコミュニティでは、様々な縁やタイミングによってメンバーが集まっています。
まずは「メンバー間の交流を深めていただくこと」を重要視しており、自身の目標としては、「本業での連携やキャリア形成支援など個々人のニーズに応えられる運営」を目指しています。
今後は他団体との連携やイベントの企画などを実行していきたいと考えています。
また、現在サステナブルコミュニティを一般社団法人化しようと考えており、その準備を進めています。
法人格を取得することで、支援できるメンバーの取り組みの幅が広がると思うので、私は管理者として、メンバーのやりたいこと・挑戦をサポートする人でありたいと考えています。
最終的な目標としては、サステナビリティに関わる全ての人をつなぐネットワークプラットフォームに発展させていきたいです。
💭bilityのひとこと
前職のサステナコンサルを経て、現在は事業会社のサステナビリティ担当に転職。支援側と実行側の両方を経験されている、ゆうじろうさんから、興味深い話をたくさん聞くことができました。
今回のインタビューのゴールは、「サステナビリティ担当の仕事の解像度をあげる」ことでしたが、いかがでしたでしょうか?
インタビューの後に、ゆうじろうさんとお話しして印象的だったのは「新卒ですぐサステナビリティ担当は難しいと思いますが、5~10年経った時に、事業会社のいちスタッフとして動かすこともできるイメージを持って欲しいです」というひとこと。
今まで、新卒はどの部署配属になるかわからないので、サステナビリティ関連職に就くのは難しい…と思っていましたが、実際にサステナビリティ担当になっている方と出会えたことで背中を押された部分もありました。
bilityに興味を持った方は、是非一度お話しましょう〜!
TwitterのDMなどからお気軽にお声がけください🌱